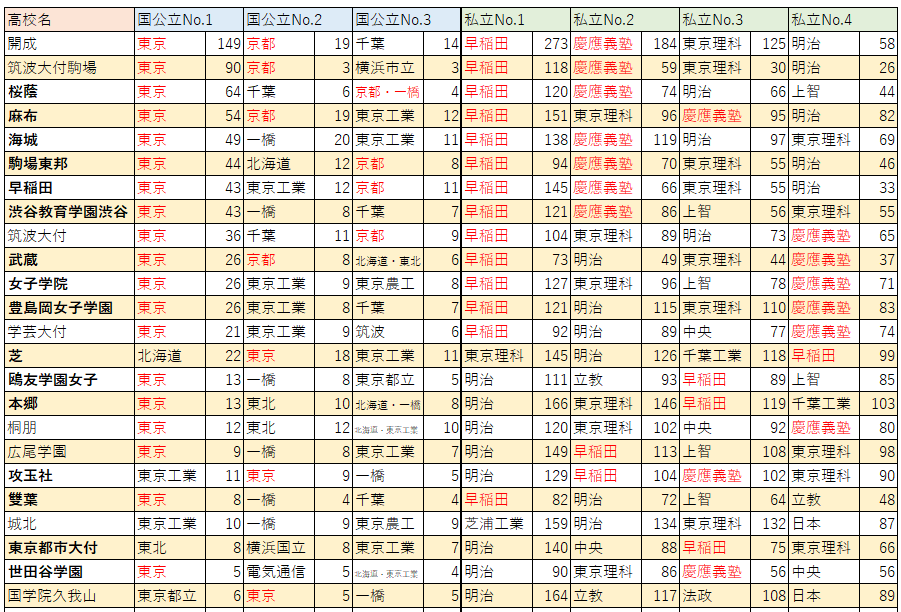今回は、国立・早慶附属高校の調査表について記載します。
私の浅い理解だと、高校受験で出願する際に必要な調査表は2種類あるのかなと思っています。
・中学校のフォーマット(中学校で作成したフォーマット)
・受験高校が指定したフォーマット
「中学校のフォーマット」「受験高校が指定したフォーマット」のどちらが多いのか。。。は分からないですが、調査表を作成する担任の先生からすると、「中学校のフォーマット」の方が助かりそうです。
逆に「受験高校が指定したフォーマット」ばかりだと。。。大変な事務作業になりそうです。
今回取り上げる、国立・早慶附属高校は、どうやら「受験高校が指定したフォーマット」のようです。。。
高校別に見ていきますが、今年の入試のもの(既に終わったもの)なので、リンクは無効になる可能性がありますし、来年度の入試では変わる可能性があります。
※取り上げるのは一般受験です。推薦や帰国生の受験は異なります。
【筑波大附属駒場高校】
(調査表の説明)
(フォーマット)※EXCELファイルあり
このフォーマットはPDFファイルですが、EXCELファイルを用意している高校は多そうです。EXCELファイルで入力して印刷する形式ですね。手書きよりは良さそうです。
それぞれの高校で、調査表の記載要領(記載方法)がありますが、依頼する際は、保護者が調査要領を印刷し、注意事項があればマーカー等を引いて先生に渡したほうが良さそうですね。先生の負担を軽減する意味でも。
【筑波大附属高校】
(調査表の説明)
(フォーマット)※EXCELファイルあり
筑駒と比較してもそこまで変わらないので、国立こそ共通化すべきではないか?と思ってしまいます。。。
【東京学芸大附属高校】
(調査表の説明)
(フォーマット)※EXCELファイルあり
上で取り上げた筑駒と筑附よりも記載内容が細かいです。「趣味・特技・資格」なんてありますが、保護者で書いて渡した方が喜ばれる?!のかな。(そんな訳ないか。)
【お茶の水女子大学附属高校】
(調査表の説明)
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/information_d/fil/chosasho_kinyu_setsumei.pdf
(フォーマット)※EXCELファイルあり
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/information_d/fil/chosasho.pdf
欠席の主な理由なんてありますが、もし何か不都合なことがあっても書くんですかね。。。「風邪等」の一択の気も。。。
次は早慶附属高校について見てみます。
【早稲田高等学院】
(調査表の説明)
(フォーマット)※PDFフォームあり
https://www.waseda.jp/school/shs/assets/uploads/2023/09/fomat_ippan2024_1.pdf
説明とフォーマットが同じファイルになっています。
この高校はEXCELファイルではなく、PDFフォームですね。PDFファイルから情報を登録する感じのようです。学校では珍しいタイプなのかもしれません。
【早稲田実業高校】
(調査表の説明) ※説明はあまりなさそうです。
https://www.wasedajg.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2023/10/2024h_bosyuyoukou.pdf
(フォーマット)※EXCELファイルあり
https://www.wasedajg.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2023/10/2024h_tyousasyo.pdf
比較的シンプルな様式のようです。
【早稲田本庄高等学院】
(調査表の説明)
(フォーマット)※EXCELファイルあり
https://www.waseda.jp/school/honjo/assets/uploads/2023/10/11268e05015f0acf06abe210e6728990.pdf
説明とフォーマットが同じファイルに書かれています。早稲田高等学院と早稲田本庄高等学院はフォーマット合わせれば良いのに。。。
【慶應義塾高校】
※ホームページに記載がありませんでした。
【慶應義塾志木高校】
(調査表の説明)
https://www.shiki.keio.ac.jp/docs/2024shikiippan-1.pdf
(フォーマット)※EXCELファイルなし
https://www.shiki.keio.ac.jp/docs/2024shikiippan-2.pdf
慶應志木はEXCELファイルはないようです。全て手書きのようです。。。
【慶應義塾女子】
(調査表の説明)
https://www.gshs.keio.ac.jp/common/pdf/2024nyushiyoko_ippankikoku.pdf
(フォーマット)※EXCELファイルなし
https://www.gshs.keio.ac.jp/common/pdf/2024shutsuganshorui_ippankikoku.pdf
この高校は、入学志願書は生徒と保護者の記載が必要ですね。
パパンダさんが過去に記載してくれています。
※変更点があるかもしれません。
(追記)出願についてあれこれ | 中学受験をさせなかった娘が高校受験で難関校を目指していたブログ
(おまけ)出願についてあれこれ | 中学受験をさせなかった娘が高校受験で難関校を目指していたブログ
慶應の附属は。。。ホームページがスマホ用に対応していなかったり、システム系が他の学校と比較して遅れているのかしら。。。
いずれにしても担任の先生には調査表に関しても面談等で早めに伝えるようにしたいと思います。